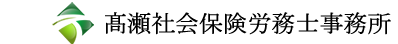建設業許可に必要な要件は
建設業許可に必要な要件は、1.経営業務の管理責任者、2.専任技術者、3.社会保険の加入、4.財産的要件、5.欠格要件、6.誠実性の6つがあります。これらのいずれかが欠けていれば許可は取得できません。
1.経営業務の管理責任者とは、「会社の社長や取締役、個人事業主をやったことがある人がいるかどうか」です。経営業務の管理責任者は、「常勤」であることが必要です。
この「経営業務の管理責任者」には要件を満たすための方法がいくつかありますが、一番多いパターンは会社の社長や取締役、個人事業主を「通算で5年」経験していることです。通算ですので、連続していなくてもOKです。まずは建設業の社長や取締役、個人事業主として「通算5年」という要件に該当しているかを確認しましょう。
他の方法としては、経営業務の管理責任者として他社で経験を積んだ人(他の会社で役員をしていた、個人事業主をやっていたといった人)を、自社の役員として連れてくることが可能であれば、その方を経営業務の管理責任者とすれば、自社の経営業務の管理責任者の要件を満たすことができます。ただし、この場合も、経営業務の管理責任者は「常勤」であることに注意が必要です。
2.次に、専任技術者についてですが、事務所に常勤する技術者が「業種ごと」必要になります。
この技術者として認められる要件としては、「資格」または「実務経験+学歴」になります。この専任技術者も「常勤」であることが必要です。また、この専任技術者については、本店・支店といった「営業所ごと」に必要になります。
この専任技術者は、営業所で工事の契約や交渉関連の業務を行うことから、当然専門の業種の技術的なことを知っている必要があります。つまり、資格や実務経験等がないとできないということになります。工事契約、交渉関連の業務を行うために、営業所ごとにいなければ迅速かつ適切な対応ができないため、「営業所ごと」に必要になります。
専任技術者については「資格」で証明した方が圧倒的に有利です。どの資格が、どの業種の建設業許可を取得できるかについては、兵庫県の手引きに記載があります。しかし「実務経験」での証明となる難しくなります。学歴によって必要な実務経験年数は変動しますが、所定の学科を出たことがない場合は、実務経験だと「10年」必要になります。※実務経験については、高校が所定の学科(業種ごとに必要な学科が異なります。下記の表を参照)を卒業している場合は5年、専門学校や大学を卒業している場合は3年に短縮されます。また、とても大事なポイントですが、経営業務の管理責任者と専任技術者は、それぞれの要件を満たすことができるのであれば、同一人物でもOKです。
3.社会保険の加入についてですが、ここでの社会保険は、「雇用保険、健康保険、厚生年金保険」のことを指しています。
労災保険は、ここでいう加入要件にはなっていません。これらの適用になる事業所については、適用事業所になった旨の届出を提出していることが許可の取得要件になります。当事務所は社会保険労務士事務所でもあるため加入についてご心配の場合はご相談ください。
4.次に、財産的要件についてですが、建設業は、金額の大きい工事が多いことから、材料の購入費にお金がかかりますので、資金繰りの観点から一定の財産を持っていることが必要になります。
一般建設業許可と特定建設業許可で、この財産的要件が異なってきます。
一般建設業の場合、次のいずれかに該当することが必要です。
①自己資本の額が500万円以上であること。
②500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
③許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること。
特定建設業の場合、次の「すべて」に該当することが必要です。
①欠損の額が資本金の額の20パーセントを超えていないこと。
②流動比率が75パーセント以上であること。
③資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること。
一般建設業の場合、直前の決算書の貸借対照表における「純資産合計」の額が500万円以上あるかで判断します。直前の決算書で証明できない場合は、銀行にいって残高証明書を取ってくる必要があります。
5.次に、欠格要件についてですが、下記の「どれか」に法人の代表者や取締役、個人事業主が該当すれば、建設業許可が取得できません。
ア 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始決定を受け復権を得ない者
イ 不正の手段により許可を受けたこと等によリ、その許可を取り消され、その取消しのHから5年を経過しない者
ウ 許可の取消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
エ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
オ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった口から5年を経過しない者
カ 次の法律に違反し、又は罪を犯したことにより罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(ア)建設業法
(イ)建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
(ウ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(エ)刑法第204条(傷害)、第200条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の2(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)又は第247条(背任)の罪
(オ)暴力行為等処罰に関する法律
キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員、又は同号に規定する暴力団員でなくなったHから5年を経過しない者(以下暴力団員等という。)
ク 暴力団員等が、その事業活動を支配する者
※ 刑の執行猶予中も、刑に処せられているため建設業許可は取得できず、破産手続開始決定を受けて復権していない人も建設業許可を取得できません。
役員の1人が欠格要件に該当していることにより、建設業許可の要件を満たさなくなるのであれば、その役員を退任させるという方法をとれば、欠格要件に該当しないことになります。また、許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているときも欠格要件に該当することになります。
6.最後に、誠実性についてですが、法人の代表者や取締役、個人事業主が、請負契約の締結や履行に際して詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為をしていないこと、工事内容・工期等について請負契約に違反する行為をしていないといったことが挙げられます。その他、建築士法、宅地建物取引業法の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者は、誠実性の要件を満たさないものとして取り扱われます。
以上が、建設業許可を受けるために必要な要件になります。
上記のほか許可・人事・労務に関するお困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。
相談料
初回の相談は無料です。
お問い合わせ先
髙瀬社会保険労務士事務所
社会保険労務士 髙瀬敦史
〒6 7 7 - 0 0 5 7 西 脇市野村町茜が丘1 0 番地の2
T E L : 0 7 9 5 - 2 1 - 2 0 3 8